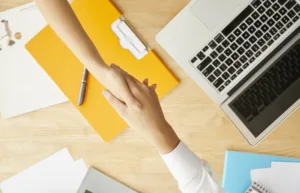目次

日本では、製造業や農業、介護分野を中心に外国人技能実習生が活躍しています。しかし、具体的に「技能実習生とはどのような制度なのか」「特定技能制度との違いは何か」「今後どのように変わっていくのか」について理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、技能実習生制度の目的や概要、受け入れ方法、今後の制度改正の動向まで、わかりやすく解説します。
技能実習生とは
技能実習生とは、開発途上国などの外国人が日本の企業で一定期間就労し、技能や技術を学び母国の経済発展に活かすことを目的とした制度で来日する人材です。
技能実習制度が1993年に創設されて以来、その在留人数は増加傾向にあり、2024年10月末時点では約47.5万人が在留しています。(参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点))
特に建設業、食品製造業、農業、介護といった人手不足が深刻な分野での貢献が大きく、現場では欠かせない存在となっています。
技能実習制度の目的
技能実習制度の最大の目的は「開発途上国への技能移転」にあります。日本で習得した技能・技術・知識を母国で活かし、産業発展や経済成長に寄与してもらうことが期待されています。
一方で、日本国内における労働力確保の側面もあり、実態としては外国人労働者の受け入れ手段となっているのが現状です。そのため近年は「人権保護」や「制度運用の見直し」も求められています。
特定技能制度との違い
特定技能制度は、2019年に創設された新たな在留資格で、人手不足が深刻な16分野(介護、外食業、建設業など)での就労を認めるものです。
技能実習制度と特定技能制度の主な違いは以下の通りです。
| 技能実習制度 | 特定技能制度 | |
| 目的 | 日本の先進技術や作業方法を母国で活かしてもらうため | 人手不足の解消企業の即戦力人材を確保するため |
| 在留期間 | 原則1~5年 | 1号は最長5年、2号は更新可で永続も可能 |
| 試験 | 不要(母国で送り出し機関選考) | 技能・日本語試験必須 |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内で転職可能 |
| 対象職種 | 91職種168作業 | 16分野 |
特定技能制度については以下の記事でも詳しく解説しています。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
2027年6月までに「育成就労制度」への移行が決まっている
技能実習制度は、2027年6月までに廃止され、新たに「育成就労制度」へと移行予定となっています。
育成就労制度では、技能実習と特定技能の双方の特徴を踏まえ、より就労目的を明確化し、転職制限を緩和することで人材育成と労働力確保を両立する仕組みになる予定です。
育成就労制度へ移行する背景とは
移行の背景には、技能実習制度における問題点が挙げられます。
- 制度の本来目的である技能移転と、実際には労働力依存となっている現実とのギャップ
- 実習生の人権侵害につながる課題(長時間労働、ハラスメント、不当解雇などの報告)
- 転職の自由が極端に制限され、劣悪な職場環境から抜け出せない
これらを踏まえ、育成就労制度では、本来の人材育成を制度の中心に据えること、就労目的を明確化し転職制限を緩和すること、そして労働条件や労働環境の適正化を徹底することなどの改善が盛り込まれています。
技能実習生の在留資格
技能実習生は「技能実習」という在留資格で入国します。区分は1号・2号・3号に分かれており、それぞれ在留期間が異なります。
- 技能実習1号:入国1年目。基礎的な技能習得を目的とする
- 技能実習2号:試験合格後、最長3年間滞在可能
- 技能実習3号:優良企業のみ対象、さらに2年間延長可
つまり最大で5年間、日本で技能実習を継続できる仕組みです。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
技能実習生の対象職種
2025年3月時点で、技能実習の対象職種は91職種168作業に及びます。
この対象職種は、法務省や厚労省によって定期的に見直されており、国際協力や業界の人材育成計画に基づいて追加・削除されることがあります。
- 農業・林業関係(3職種7作業)
- 漁業関係(2職種10作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- 食品製造関係(11職種19作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(17職種34作業)
- その他(21職種39作業)
- 社内検定型の職種・作業(2職種4作業)
技能実習生を受け入れる方法
技能実習生を受け入れる方法には「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。
企業単独型
企業単独型は、日本の企業が海外現地法人や取引先の従業員を直接受け入れ、自社で技能実習を行う方式です。海外支店や海外の取引先がある場合、後述する団体監理型を介さずに受け入れることが可能であり、受け入れまでの流れとしては以下の通りです。
- 送り出し国政府への申請
- 日本での技能実習計画作成・認定申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- ビザ取得
- 来日・技能実習開始
例えば製造業大手では、ベトナムやタイ現地工場から従業員を招き、数年間日本で技術を習得させた後、現地に戻って指導的立場につけるケースが多くあります。
団体監理型
団体監理型は、監理団体(商工会議所、農協、業界団体など)が技能実習計画を監理し、実習実施者である企業に技能実習生を配属する仕組みです。
海外支店や取引先がない一般企業はこの団体監理型を利用する必要があり、企業の多くが利用している最も一般的な方式です。
この場合の流れは以下の通りです。
- 送り出し機関と監理団体を通じて申請
- 実習計画作成
- 監理団体による審査
- 在留資格認定証明書交付申請
- ビザ取得
- 来日・技能実習開始

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
技能実習生を受け入れる際の注意点
技能実習生を受け入れる際には、以下の点に注意する必要があります。
監理団体の選定
監理団体の選び方は極めて重要です。実績や指導体制、日本語教育サポート、トラブル対応力などを必ず確認しましょう。一定の要件を満たしている場合は、優良な管理団体であることが国から認定してもらうことができます。監理団体のホームページなどから確認してみましょう。
受け入れ上限人数
企業が受け入れ可能な人数は、常勤職員数に応じて決まっています。
| 常勤職員数 | 基本人数枠 |
| 301人以上 | 常勤職員数の1/20人 |
| 201人~300人 | 15人 |
| 101人~200人 | 10人 |
| 51人~100人 | 6人 |
| 41人~50人 | 5人 |
| 31人~40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
上記を参考に、受け入れ人数を超えないよう計画を立てましょう。
環境整備や技能実習計画の作成
技能実習計画は入国前に作成し、実習内容、教育計画、評価方法を詳細に記載します。また、寮や生活支援環境の整備、日本語指導の実施も必須です。受け入れ企業としては、こうした環境整備や計画の策定、関係機関への届出など義務を抜け漏れなく果たす必要があります。
これらが不十分だと入管審査で不許可となる場合があるため注意が必要です。
まとめ
技能実習生とは何か、制度の目的、特定技能制度との違い、今後の育成就労制度への移行背景、在留資格、対象職種、受け入れ方法や注意点について解説しました。
技能実習制度は、日本にとって重要な労働力確保手段であると同時に、開発途上国への技術移転という大きな役割も果たしています。しかし、2027年には育成就労制度への移行が決まっており、企業としても最新情報を常にキャッチアップし、適正な受け入れ体制を整えることが求められます。
今後も技能実習生制度や育成就労制度に関する最新情報をチェックし、外国人雇用戦略に役立てていきましょう。
外国人労働者の受け入れサポートは『アイデムグローバル』
外国人労働者の受け入れをお考えの方は、特定技能外国人材の採用から就業支援、生活サポート、届出代行までトータルで支援する『アイデムグローバル』をご検討ください。
4,400名以上の支援実績に基づき、企業と個人にあったサポートをご提案します。
- 行政対応もフルサポート
- 支援計画書の作成から定着支援までワンストップ
- 全国対応・業界特化型プランあり
特定技能外国人材の支援にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。