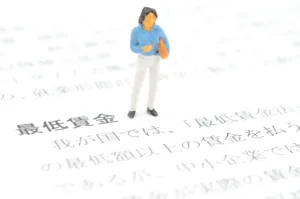目次

日本人を雇用する際には加入が必須となる社会保険が、外国人労働者の場合はどうなるのか疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。
この記事では、外国人労働者の社会保険の加入について解説します。加入が必要な保険の種類や、雇用の際に気をつけたいポイントなどについてもまとめました。
外国人労働者は社会保険に加入する必要がある?
日本で働く外国人労働者は、日本人と同様に社会保険への加入が法律で義務付けられており、雇用形態や在留資格に関わらず、原則として適用対象となります。
具体的に加入が必要な保険は次のとおりです。
| ・健康保険 ・労働保険 ・介護保険 ・年金保険 |
日本では外国人労働者が増加傾向にあり、2024年時点での外国人労働者数は約230万人と過去最高を記録しています。この背景もあり、企業側も正しい保険加入の知識が求められています。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
外国人労働者に加入が必要な保険①健康保険
健康保険は、社会保険と国民健康保険に分かれており、外国人労働者の条件によって加入する保険がどちらになるかが変わります。
社会保険
適用対象者・適用除外者
社会保険の加入適用対象者は、原則として「常時雇用されている労働者」です。具体的には、以下のような条件を満たす場合、健康保険への加入が義務づけられます。
| ・1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同一事業所の正社員のおおむね4分の3以上であること ・雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあること |
一方で、以下のような場合には適用除外とされることがあります。
| ・海外から短期で来日している技能実習生で、滞在期間が3ヵ月未満の予定である場合 ・雇用契約が非常に短期間(2ヵ月未満)で、かつ更新の見込みがない場合 |
外国人労働者の家族の扶養について
健康保険に加入した外国人労働者は、その家族を扶養に入れることも可能です。扶養に入れる条件は、日本人と同様に以下のとおりです。
| ・被扶養者が年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること ・被保険者からの仕送り等により生活していること ・原則として日本国内に居住していること(ただし、例外として海外在住の家族も認められる場合があります) |
この扶養制度により、医療費の自己負担が軽減されるため、多くの外国人労働者にとって大きなメリットとなります。
国民健康保険
企業に雇用されていない外国人労働者や、個人事業主として働く外国人は、社会保険に加入することができない代わりに国民健康保険への加入が必要です。
こちらは市区町村が運営しており、保険料は前年の所得に応じて決定されます。
具体的な条件は以下のとおりです。
| ・日本に3ヵ月を超えて滞在していること ・社会保険に加入していないこと ・永住者や中長期在留者の在留資格を持っていること |
外国人労働者に加入が必要な保険②労働保険
労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称で、すべての労働者を対象にした重要な制度です。健康保険と同様に、雇用形態や国籍を問わず、外国人労働者にも適用されます。
労働保険では失業時や業務中の事故・病気などに対する補償を受けることができ、外国人労働者の生活の安定にも大きく寄与します。
雇用保険
雇用保険は、働く人が失業したときや育児・介護休業を取る際に、生活を支えるための給付金が支給される制度です。外国人労働者も、条件を満たせば日本人と同様に雇用保険の対象となります。
雇用保険は、厚生労働省が所管し、全国のハローワークを通じて手続きがおこなわれます。
加入の要件
外国人労働者が雇用保険に加入するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
| ・31日以上の雇用見込みがある ・1週間の所定労働時間が20時間以上である ・資格外活動(留学生のアルバイト等)ではない |
例えば、アルバイトであっても週20時間以上働き、1ヵ月以上の雇用契約がある場合は、雇用保険の加入対象となります。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中の事故によってケガや病気になった場合に、医療費や休業補償などをおこなう制度です。
労災保険は、事業主(雇用主)が100%負担するため、労働者本人が保険料を支払う必要はありません。
労災保険で受けられる主な給付内容は次のとおりです。
| ・療養補償給付:治療費は全額支給(自己負担なし) ・休業補償給付:労災による休業4日目以降、平均賃金の80%相当が支給される ・障害補償給付:後遺障害が残った場合の一時金や年金給付 ・遺族補償給付:死亡事故に対する遺族への給付金 |

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
外国人労働者が加入する保険③介護保険
外国人労働者が介護保険に加入するのは、次の条件に当てはまる場合です。
| ・40歳以上65歳未満 ・日本国内に住民票がある ・社会保険に加入している |
つまり、40歳以上の外国人労働者が企業で社会保険に加入している場合、自動的に介護保険料も給与から天引きされます。
外国人労働者が加入する保険④年金保険
外国人であっても、就労資格があり、適法に日本国内で働いていれば、日本人と同様に年金保険への加入が義務付けられています。
日本の年金制度には以下の2種類があります。
| ・国民年金(基礎年金):自営業者、フリーランス、非正規労働者などが対象 ・厚生年金保険:企業に雇用され、社会保険に加入している正社員やアルバイト等が対象 |
外国人労働者に適用される特別な制度について
年金保険では、外国人労働者にのみ適用される特別な制度として「脱一時金」と「社会保障協定」の2つがあります。
脱退一時金
外国人労働者が日本で一定期間働いたあと、母国に帰国して年金を受け取る予定がない場合、「脱退一時金」を申請することで支払った年金保険料の一部を返金してもらうことができる制度です。
脱退一時金の主な条件は以下のとおりです。
| ・日本を出国し、住民票を抹消していること ・最後の年金加入日から2年以内に申請すること ・厚生年金または国民年金の加入期間が6ヵ月以上あること ・年金を一度も受給していないこと(老齢年金等) |
外国人労働者にとっては収入に関わる大きなポイントとなるため、事前に説明しておくことをおすすめします。
社会保障協定
社会保障協定は、日本と他国の間で結ばれる協定で、年金制度の二重加入や年金受給の不利益を防ぐための仕組みです。
現在、日本は26ヵ国以上と協定を締結・発効しており、アメリカ、ドイツ、韓国、フィリピン、インドなどが含まれるため、外国人労働者の出身国を確認しておきましょう。
社会保障協定がある国からの駐在員などは、日本での保険料負担を免除できるケースもあり、コスト削減にもつながります。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
外国人を雇用する際に気をつけたいポイント
外国人を雇用するにあたって、賃金の設定と在留資格について気をつけておきましょう。
賃金の設定について
外国人労働者にも日本人と同様に「最低賃金法」や「同一労働同一賃金法」が適用されます。外国人労働者であることを理由に、賃金を低く設定するといったことをすることは認められません。
適正な賃金でない場合、在留資格が認められないこともあるため、気をつけましょう。
関連記事:外国人労働者の最低賃金は?注意したい点や平均賃金、税金との関係を解説
在留資格について
雇用する外国人の在留資格を事前に確認し、不法滞在にならないよう在留期限をチェックしておくこともポイントです。
在留期間の更新は、期限の3ヵ月前から可能なため、余裕を持って準備しておきましょう。
外国人雇用のサポートは登録支援機関の活用がおすすめ
外国人を雇用するには、保険制度や法律、必要な書類などの準備を頭に入れておかなければなりませんが、煩雑で慣れない手続きのため苦労する企業も少なくありません。
そこで、日本で働きたい外国人と外国人を雇用したい企業の双方をサポートする「登録支援機関」を活用することで、外国人雇用を円滑に進めることができます。
アイデムグローバルでは、外国人の人材探しから契約締結後の手続き、サポートまでをワンストップで支援します。
特定技能人材4,400名以上の内定実績をもとに、ベトナム語・ミャンマー語・英語・韓国語・カンボジア語・インドネシア語の6ヵ国語に対応しているため、人材にも企業にも寄り添った支援が実現可能です。
特定技能外国人材の受入れ・人材探しを検討している企業様は、下記からお気軽にお問合せください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
まとめ
外国人労働者も日本人と同様に社会保険の加入が必須ですが、先の受給となる年金においては外国人労働者が不利にならないよう特別な制度が設けられています。
これらを外国人労働者に企業から説明し、理解を得て働くことは企業や日本への信頼につながるため、まずは企業側がしっかりと理解を深めておきましょう。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。