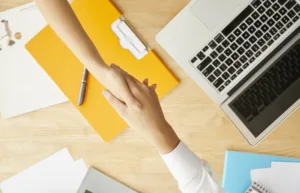目次

2024年6月、30年以上続いた技能実習制度が廃止され「育成就労制度」へと移行することが決定されたことで、日本の外国人労働者受け入れ制度に大きな転機が訪れました。
本記事では、制度変更の背景や新制度の特徴、企業や外国人にとっての影響、そして今後の制度運用の見通しまで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、2024年6月に国会で成立した新たな外国人受け入れ制度であり、これまでの技能実習制度に代わる形で創設されました。主な目的は、日本国内の慢性的な人手不足を補うこと、そして外国人労働者が安心して長期的に働ける環境を整備することにあります。
これまでの技能実習制度では「技能の母国への移転」が建前とされていたものの、実際には国内の労働力確保が実態でした。育成就労制度はこの矛盾を是正し、外国人の職業能力の向上とキャリア形成支援を明確な制度目的としています。
移行期間について
制度の完全施行に向けた移行期間は、2024年6月の法成立から最大3年間、すなわち2027年6月までとされています。この間に既存の技能実習生も新制度に段階的に移行可能となっており、関係機関には丁寧な移行対応が求められています。
育成就労制度の目的
育成就労制度は、将来的に特定技能1号への移行を見据え、人材確保を目的としています。
育成期間(最大3年)を経て、技能習得や日本語能力、評価試験など一定の条件を満たせば、スムーズに特定技能1号へと移行できます。このような設計により、外国人労働者にとってもキャリアの連続性が確保され、企業側も長期的な人材戦略を描きやすくなります。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
技能実習制度の廃止が決まった背景
技能実習制度は1993年に導入され、当初は「開発途上国への技能移転」を目的としていました。しかし制度運用の実態は、労働力確保が主眼となっており、本来の趣旨から逸脱しているとの批判が国内外から相次ぎました。
制度廃止に至った大きな理由は以下の通りです。
- 技能の移転という目的に対し、労働力依存となっている現実とのギャップ
- 実習生の人権侵害(長時間労働、ハラスメント、不当解雇など)
- 転職の自由が極端に制限され、劣悪な環境からの離脱が困難
これらの課題を根本的に解決するため、新制度への移行が決定されました。
育成就労制度と技能実習制度の違い
育成就労制度と技能実習制度の違いについて、以下でまとめました。
| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |
| 在留期間 | 原則3年 | 最長5年(1号:1年、2号・3号:2年) |
| 受け入れ対象分野 | 特定産業分野に限定(16分野を中心に設定) | 約90職種165作業 |
| 分野ごとの上限人数 | 分野別に依存率を設定(例:建設業は10%以内) | 上限規定なし(偏在の傾向あり) |
| 日本語能力の評価 | 日本語能力試験N4以上などを要件化 | 明確な日本語力基準はなし |
| 転籍 | やむを得ない事情・本人希望で可能(条件あり) | 原則不可 |
| 受入れ機関ごとの人数 | 対象分野ごとに上限を設定 | 企業の常勤職員数に応じて変化 |
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
在留期間
育成就労制度では、外国人労働者は原則として最長3年間の在留が認められます。この育成期間を終えた後、一定の条件を満たせば「特定技能1号」への在留資格の変更が可能です。
これにより、最大でさらに5年間の継続的な在留・就労が認められることになります。特定技能1号に移行することで、より高い専門性と定着が期待される制度設計となっています。
受け入れ対象分野
技能実習制度では約90職種(165作業)が対象でしたが、育成就労制度では「特定産業分野」のみを対象とし、より明確に人手不足が深刻な業界に限って受け入れをおこなう形となります。具体的には、介護、外食、建設、宿泊、農業、製造など、特定技能1号で設定されている16分野が中心です。
この限定により、外国人労働者の受け入れが漫然と拡大することを防ぎ、制度本来の目的に即した分野での実効性が高まると期待されています。
| 分野番号 | 育成就労・特定技能分野名 | 特定技能2号 | 備考 |
| 1 | 介護 | 在留資格:介護(要介護福祉士) | |
| 2 | ビル クリーニング | 有り | |
| 3 | 工業製品製造業 | 有り | |
| 4 | 建設 | 有り | |
| 5 | 造船・舶用工業 | 有り | |
| 6 | 自動車整備 | 有り | |
| 7 | 航空 | 有り | ※特定技能のみ |
| 8 | 宿泊 | 有り | |
| 9 | 自動車運送業 | 2024年~ ※特定技能1号のみ | ※特定技能のみ |
| 10 | 鉄道 | 2024年~ ※特定技能1号のみ | |
| 11 | 農業 | 有り | |
| 12 | 漁業 | 有り | |
| 13 | 飲食料品製造業 | 有り | |
| 14 | 外食業 | 有り | |
| 15 | 林業 | 2024年~ ※特定技能1号のみ | |
| 16 | 木材産業 | 2024年~ ※特定技能1号のみ | |
| 17 | 物流倉庫 | 2026年~ | |
| 18 | 資源循環 (廃棄物処理) | 2026年~ | |
| 19 | リネンサプライ | 2026年~ |
分野ごとの上限人数
受入れ機関側の要件として、現時点では「特定産業分野」に分類される業種であることと、受入れ人数の上限が設定されることは発表されていますが、それ以外の詳細な要件についてはまだ検討段階にあります。
たとえば、受け入れ機関としての認定条件や評価指標、過去の制度違反歴の有無による審査基準など、制度運用に必要な具体的ルールは今後の省令・ガイドラインの策定を待つ状況です。
日本語能力の評価
受け入れには日本語能力の評価も重要な要素とされています。技能実習制度では明確な日本語要件がありませんでしたが、育成就労制度では段階的な語学力向上を制度として求めるようになりました。
以下のように、各段階での基準が設定されています。
- 就労前:日本語能力試験N5に合格、または認定された日本語教育機関で同等レベルの講習を受講していること
- 1年目終了時点:日本語能力試験N5の合格に加え、技能検定基礎級などの基礎的な技能試験にも合格していること
- 3年目終了時点:日本語能力試験N4に合格しており、技能検定随時3級や特定技能1号評価試験にも合格していること
これらの要件は、外国人労働者が日本社会や職場に円滑に適応し、将来的なキャリアパスへ進むための基礎力を担保するものです。
転籍
育成就労制度では、労働者の保護と職場選択の自由を尊重する観点から、「やむを得ない事情による転籍」と「本人の意向による転籍」が可能になります。
まず、やむを得ない事情による転籍としては、パワハラ、長時間労働、賃金未払いなどの深刻な労働問題が発生した場合に、本人の安全と権利を守る観点から迅速に転籍が認められます。これにより、不当な扱いから逃れるための制度的なセーフティーネットが確保されます。
また、本人の意向による転籍は、以下の要件を満たすことで可能です。
- 原則として同一事業所での就労期間が1年以上であること
- 転籍先の業種が現在の就労分野と同一であること
- 転籍後の受入れ機関が適切な育成計画を策定・実施できる体制を有していること
- 受入れ機関が労働法規・就労ルールを遵守していること
- 転籍希望が本人の自由意思に基づくこと
- A1〜A2相当の日本語能力試験に合格していること
これらの条件を満たすことで、無秩序な人材流動を防ぎつつ、より良い職場環境の選択肢が確保されます。これにより、無秩序な人材流動を防ぎつつ、本人のキャリア形成や就労環境改善の選択肢が広がります。
受入れ機関ごとの人数
技能実習制度では、受入れ機関の常勤職員数に応じて技能実習生の人数が定められています。例えば常勤職員数が30人以下の場合は3人、31〜40人以下の場合は4人、などです。
対して育成就労制度では、対象分野ごとに受け入れ人数が設定されることが発表されています。それ以外の詳細はまだわかっていないため、今後の決定を待ちましょう。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
受入れ機関側の要件は?
受入れ機関側の要件として、現時点では「特定産業分野」に分類される業種であることと、受入れ人数の上限が設定されることは発表されていますが、それ以外の詳細な要件についてはまだ検討段階にあります。
たとえば、受け入れ機関としての認定条件や評価指標、過去の制度違反歴の有無による審査基準など、制度運用に必要な具体的ルールは今後の省令・ガイドラインの策定を待つ状況です。
監理団体は監理支援機関に名称変更
従来の「監理団体」として扱われていた団体は、制度移行に伴い「監理支援機関」へと名称が変更されます。新たな役割としては、育成計画の進捗確認、法令順守の監督、労働者とのコミュニケーション支援などがあり、制度の透明性と適正性を担保する存在となります。
この監理支援機関は、育成就労外国人と実施者との雇用関係の調整や、育成計画が適切に運用されているかどうかを監督する立場として位置付けられ、今後は許可制となります。許可を受けるためには、業務遂行能力、安定した財政基盤、そして外部監査人の設置など、厳格な条件をクリアする必要があります。
また、利害関係の排除を徹底する観点から、育成就労実施者と密接な関係を持つ職員は、その事業所に対する業務に関与できないとされており、監理支援責任者の選任も義務付けられています。これにより、公平で独立した監理体制の構築が目指されています。
まとめ
育成就労制度は、技能実習制度の限界を認識したうえで設計された、より実効性のある外国人受け入れ制度です。特定技能1号との連携、適切な労働環境の整備、キャリア支援体制の明確化などを通じて、外国人と企業、そして日本社会の持続可能な共生に貢献することが期待されています。
特定技能外国人の雇用・サポートなら『アイデムグローバル』
特定技能外国人の雇用を検討している方は、外国人材の採用から就業支援、生活サポート、届出代行までトータルで支援する『アイデムグローバル』をご検討ください。3,500名の支援実績に基づき、企業と個人にあったサポートをご提案します。
- 行政対応もフルサポート
- 支援計画書の作成から定着支援までワンストップ
- 全国対応・業界特化型プランあり
特定技能外国人材の支援にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶アイデムグローバルへのお問合せはこちら

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。